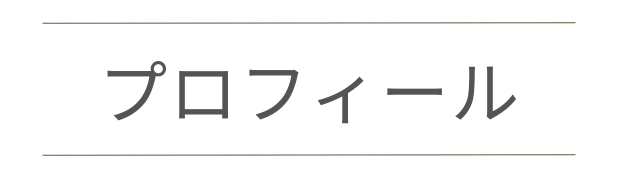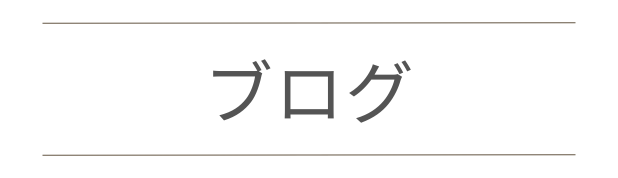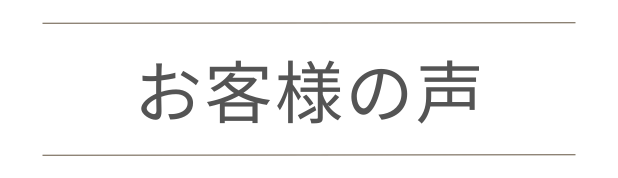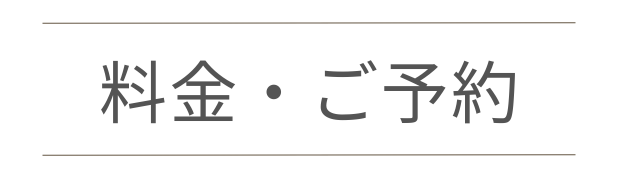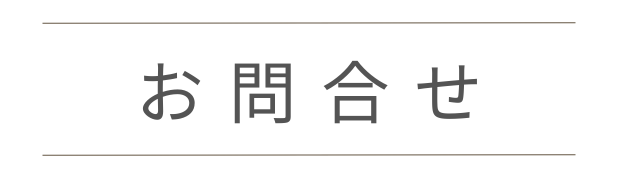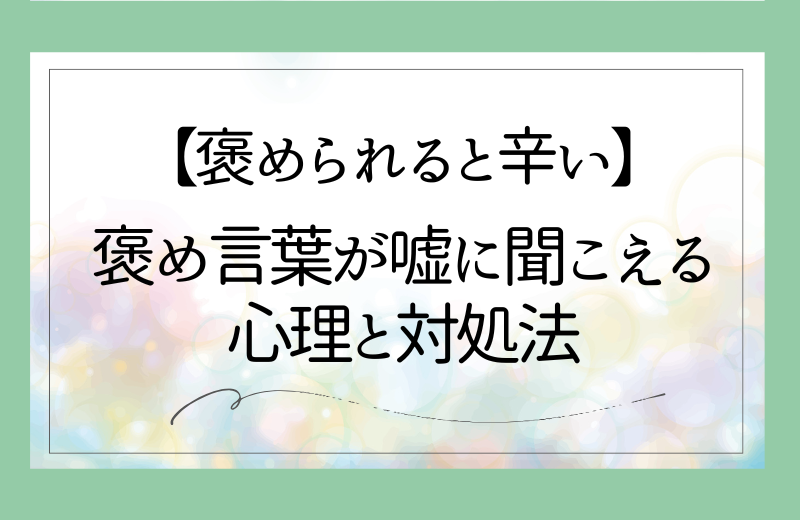
「すごいね」「頑張ってるね」——そう言われると、嬉しいはずなのに、なぜか心がザワザワしてしまう。そんな経験はありませんか?
むしろ居心地が悪くなって、話題を変えたくなったり、「いやいや、そんなことないです」と否定してしまったり……。周囲には伝わらないけれど、自分の中では小さな緊張や違和感が走っている、そんな感覚。
それは、「褒められること」そのものが、あなたにとって嬉しかったり安心できることではないからかもしれません。
このブログでは、「褒められると辛い」と感じる心理の正体と、その背景にあるインポスター症候群やアダルトチルドレンとの関係性について解説していきます。
「なぜ私は素直に受け取れないんだろう?」という問いに、少しでもヒントが届きますように。そして、褒め言葉を“プレッシャー”ではなく“支えになるもの”として受け取れるようになるための一歩になれたらと思います。目次
「褒められると辛い」の正体|インポスター症候群
「褒められると嬉しい」——それは、一般的には当たり前の反応かもしれません。でも実際には、「嬉しいよりも居心地が悪い」「素直に信じられない」「なぜか謝りたくなる」と感じる人が少なくありません。
その背景にある心理として注目されているのが、インポスター症候群(Impostor Syndrome)です。
インポスター症候群とは、自分の成果や評価を「実力ではなく、たまたま運がよかっただけ」「周囲の誤解」と感じてしまう心理傾向のこと。成功や称賛に対して自信が持てず、「本当の自分はそこまで価値がない」と思い込んでしまう状態です。
この症候群を抱えている人は、他者から褒められるたびに、こんな思いが頭をよぎります。
- 「あの人は私の本当の実力を知らないだけ」
- 「次に失敗したら、がっかりさせてしまう」
- 「期待されると、もっと頑張らないといけない」
つまり、「褒められる=仮面がバレる危険」と無意識に感じてしまうのです。
このように、インポスター症候群は「評価」や「承認」をプレッシャーとして受け取り、心の中で“否定の声”を強めてしまいます。特に、完璧主義や強い責任感を持っている人ほど、この傾向は強く現れがちです。
褒め言葉が「励まし」ではなく「脅し」に感じられるという方は、自分の中のインポスター的な思考パターンが働いている可能性があります。
このあとお伝えしていきますが、こうした反応には過去の体験や、長く染みついた「心のクセ」が関係している場合もあるのです。
あなたのお悩みお聞かせください
↓ ↓ ↓
褒め言葉が嘘に聞こえる人の特徴

「褒められると、なぜか心がザワザワする」「言葉の裏を読んでしまう」「お世辞っぽく聞こえる」——。 このように、褒め言葉を素直に受け取れない方には、いくつかの共通した特徴があります。
まず見られるのが、自己否定の強さです。自分に対する評価が著しく低く、「どうせ私なんて」「本当の私はそんな人間じゃない」といった思考がクセになっているため、 他人のポジティブな言葉を“自分に当てはまらないもの”として拒否してしまうのです。
また、警戒心や人間不信が強い傾向もあります。過去に裏切られたり、期待を持たせたあとに傷ついた経験がある方は、「褒められる=何か裏があるのでは?」と疑いをもってしまいます。
さらに、褒め言葉を“期待”として受け取り、重荷に感じてしまう人も少なくありません。 「すごいね」「頼りにしてる」と言われた瞬間に、「もっとがんばらなきゃ」「次も失敗できない」と思い詰めてしまうのです。
このように、褒め言葉が嘘に聞こえる背景には、次のような特徴が複雑に絡み合っています。
- 自己肯定感が低く、ポジティブな言葉に違和感を覚える
- 「期待に応えなければ」というプレッシャーを感じやすい
- 人からの言葉を素直に信じることに不安がある
- 表面的には明るくても、内心では自分にダメ出しをしている
褒められる=評価されることに対して、恐れや不安を感じる心のクセは、すぐに自覚しづらいもの。 ですが、こうした特徴に気づくことで、「どうして受け取れないのか」が少しずつ見えてくるようになります。
そしてその背景には、子ども時代からの体験が大きく関わっているケースも多くあるのです。
「褒められると辛い」とアダルトチルドレンとの関連性

褒め言葉を素直に受け取れなかったり、好意や承認に対して疑いを持ってしまう背景には、子ども時代の家庭環境が深く影響していることがあります。
その中でも特に多いのが、「アダルトチルドレン(AC)」と呼ばれる心の状態です。アダルトチルドレンとは、機能不全な家庭で育った影響により、大人になってからも人間関係や自己評価に困難を抱える人のことを指します。
ACの方が子ども時代に体験しがちな環境には、次のような特徴があります。
- 親が過干渉・無関心・感情的だった
- 失敗すると責められる、完璧を求められる
- 「頑張ったね」よりも「もっとできたでしょ」と言われてきた
- 感情表現を否定され、安心して甘える経験が少なかった
こうした家庭で育つと、子どもは「自分のままでは認められない」「評価は“条件付き”でしかもらえない」と学習してしまいます。
その結果、大人になってからも
- 褒め言葉を疑ってしまう
- 素直に喜べない自分に罪悪感を抱える
- 期待されることが怖くなり、距離を取ってしまう
といった反応が生まれやすくなるのです。
特に、条件付きの愛情のもとで育った人ほど、承認に対して緊張や警戒を感じます。 なぜなら「褒められる=次も頑張らないと見捨てられる」と感じてしまうからです。
アダルトチルドレンの傾向は、決して“特別な人”だけの話ではありません。
親が意図的に傷つけようとしたわけでなくても、子どもが「安心できない」「そのままの自分では足りない」と感じながら育った経験は、心に深い影響を残します。
「褒められると辛い」と感じる心のクセも、“ちゃんと理由のある心の反応”なのです。
ここでお伝えしたかったのは、「今のあなたの受け取り方には、過去の経験が関係している可能性がある」という視点です。そしてそれは、意識すること、向き合うことで、変えていくことができるものでもあります。
なお、このような“承認されることへの不安”は、アダルトチルドレンだけでなく、愛着障害の特徴として見られる場合もあります。愛着が不安定なまま成長すると、「人からの好意=不安・負担」と感じやすくなる心のクセが生まれることがあるのです。
愛着障害とアダルトチルドレンは、いずれも「安心してつながる感覚が持てなかった経験」に由来する部分があり、褒め言葉がうまく受け取れない背景に、両者の影響が重なっているケースも少なくありません。
愛着障害について詳しく知りたい方は、別の記事でご紹介していますので、そちらもあわせて参考にしてみてください。
あなたのお悩みお聞かせください
↓ ↓ ↓
「褒められるのが辛い」状態を放置する危険性

「褒められると辛い」「嬉しいはずなのに、素直に受け取れない」。 こうした反応を「性格だから」「私はそういうタイプだから」と放置してしまう方も少なくありません。
ですが、この状態をそのままにしておくと、心や人間関係にじわじわと影響が広がっていくことがあります。
まず起こりやすいのが、自己否定感の強化です。褒められるたびに「そんなわけない」「私なんて」と否定するクセが続くと、自分に対する信頼や価値の実感がどんどん薄れていきます。その結果、自己評価が安定せず、どんなに努力しても「まだ足りない」と感じてしまう“自己否定ループ”に入り込んでしまうのです。
また、対人関係にも影響が出やすくなります。 褒め言葉を受け取れないことで、相手との間に目に見えない“壁”ができたり、「どうせ本心じゃないんでしょ」と距離を取ってしまったり……。 相手の善意を疑うクセが続くと、信頼関係を築くことが難しくなり、人とのつながりが希薄になっていくこともあります。
さらに、仕事や恋愛などでも“自己価値の感覚”が持てないまま関係性に臨むと、
- 「認めてもらえない」
- 「結果を出しても虚しい」
- 「好意が負担になる」 といった感覚に苛まれやすくなります。
本来なら喜びや安心を得られるはずの場面で、なぜか自分を責めてしまう——。 その状態が続くことで、心の疲れが蓄積し、抑うつ感や不安、慢性的な孤独感へとつながるリスクもあるのです。
だからこそ、「褒められるのが苦しい」と感じたときこそ、立ち止まって自分の心を見つめ直すタイミングなのです。
「褒められると辛い」の対処法

「褒められると辛い」という感覚は、一見するとただの性格のようにも思えるかもしれません。 しかし、その多くは過去の経験や心のクセが作り出しているもの。 だからこそ、“向き合い方”を変えることで、少しずつ受け取り方も変えていくことができます。
ここでは、「考え方」と「行動」の2つの視点から、今できる対処法をご紹介します。
🧠考え方のヒント|“褒め=評価”ではなく“関係性”ととらえてみる
まず試してほしいのは、「褒められること=評価されること」という思い込みから一歩離れてみること。
褒め言葉とは、「あなたに一歩近づきたい」「あなたを認めている」という相手の感情表現のひとつです。
それを「自分にふさわしいか」「本当かどうか」とジャッジするのではなく、 “この人は私に対して、そういうまなざしを向けてくれている”と受け止めてみることから始めてみましょう。
「信じること」が難しくても、「その人の思いとして受け取る」なら、少しだけハードルが下がるかもしれません。
✋行動のヒント|“ありがとう”を、気持ちでなく言葉として練習する
「褒められても受け取れない」と感じる方ほど、「ありがとう」と返すのに心の準備がいります。
そんなときは、気持ちが伴っていなくても、まずは“言葉として”練習してみるのがおすすめです。
無理に喜んだり、リアクションを大きくする必要はありません。 ただ、「ありがとうございます」と返す練習を少しずつ積んでいくことで、 “褒められても否定しなくていい”という感覚が、少しずつ自分の中に育っていきます。
受け取れないままの自分を責める必要はありません。 少しずつ、心と反応のあいだに「ゆとり」をつくっていくこと——それが、長く続いてきた心のクセをやわらげる第一歩になるのです。
あなたのお悩みお聞かせください
↓ ↓ ↓
褒め言葉が嘘に聞こえる|このようなご相談に私ならこう向きあいます

ネットでこんなお悩みを目にしました。
「上司や同僚から『すごいね』『助かってるよ』と言われても、嘘っぽく聞こえてしまいます。本当にそう思ってるの?と疑ってしまって、嬉しいどころか、逆に居心地が悪くなるんです」
.jpg)
カウンセラーの田口れいです。
もしこの方が私のカウンセリングに来られたとしたら、まずは「その反応には意味がある」という前提でお話をお聞きします。
たとえば、「褒められると嘘に聞こえる」という感覚は、それだけ人の気持ちに敏感で、相手の裏の意図を探ってきた経験があることのあらわれでもあります。もしかしたら過去に、「褒められたあとにガッカリされた」「期待に応えられなかった」という体験があるのかもしれません。
カウンセリングでは、そんな“疑ってしまう気持ち”の奥にある本音を、一緒に少しずつ探っていきます。「信じたいけど、怖い」「期待されると苦しくなる」——こうした揺れる感情があることは、とても自然なこと。
だからこそ私は、こう問いかけます。「もし相手の言葉が本心だったとしたら、あなたはどう感じますか?」
すると少しずつ、「本当は嬉しかったのかもしれない」「信じてもいい言葉もあるのかも」というような気持ちがにじんでくるかもしれません。
こうした小さな気づきの積み重ねが、褒め言葉を信じる“練習”の始まりになります。
私がカウンセリングで大切にしているのは、「心のクセをなくす」ことではなく、「そのクセが何を守ってきたのか」に目を向けること。このようなセッションを続けながら、この方が本当に望んでいることが見えてきたら、望む未来に向けての対策を一緒に考えていきます。
セッションを受けられた方の体験談
このように、専門家のサポートを受けることで、自分の人生を取り戻すための適切な対策を取ることが可能になります。生きづらさを感じ、自分だけで対処しきれないと感じた場合は、ぜひ一度、カウンセリングを検討してみてください。
褒められると辛い悩み|よくある質問

褒められることにモヤモヤしてしまうのは、あなただけではありません。 ここでは、実際によくあるご質問と、それに対して私がどのようにお答えしているかをご紹介します。
Q1 褒められると、どう返せばいいのかわかりません。
無理に明るく振る舞ったり、完璧なリアクションをしようとしなくても大丈夫です。 「ありがとうございます」と言うだけでも、十分素敵な返しになります。 これは、自己肯定感が育ちにくかったアダルトチルドレンの方に特に多いお悩みです。 “褒め=評価”という思い込みから少し離れて、「気持ちを受け止める」ことを目指してみてくださいね。
Q2 「どうせお世辞でしょ?」と思ってしまう私は、性格が悪いのでしょうか?
いいえ、それは防衛反応のひとつです。信じてガッカリしたくない気持ちが、先に出てしまっているだけ。 インポスター症候群の傾向がある方は、他人の言葉を素直に受け取ることに不安を感じやすいもの。 「信じたいけど怖い」という気持ちの奥には、誠実で傷つきやすいあなたの一面があるはずです。
Q3 褒められると、なぜか“試されている気”がしてしまいます。
これは、条件付きの愛情で育った方に見られやすい反応です。 「ちゃんとしないと愛されない」「期待に応えなきゃ見捨てられる」——そんな思いが、心のどこかに残っているのかもしれません。 アダルトチルドレンの課題を持つ方は、褒め言葉に“次へのプレッシャー”を感じやすい傾向があります。
Q4 「褒められるとしんどい」という気持ち、どう伝えたらいいですか?
信頼できる人であれば、少しずつ自分の感じ方を言葉にしてみるのもいいかもしれません。 「嬉しいけど、どう反応していいかわからなくて」など、自分の正直な気持ちを伝えることで、相手との関係性がより自然になることもあります。 ただ、無理に伝えようとしなくて大丈夫。まずは自分の気持ちに気づくことから始めていきましょう。
Q5 一人でこの気持ちに向き合っていけるか不安です。
そのお気持ち、とてもよくわかります。 褒められることに違和感を覚える背景には、長い間身につけてきた“心のクセ”や“思い込み”が関係していることがあります。 それらは一人で抱えるには、時にとても重たいものです。もし「話すだけでも少し楽になるかも」と思えたら、専門家に相談するという選択肢を検討してみてもいいかもしれません。 安心できる関係の中で、自分の反応に少しずつ優しく目を向けていくことで、心がほどけていくこともあります。
まとめ|褒め言葉を自分の力にするために
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
いかがでしたか?
「褒められるのに嬉しくない」「褒め言葉が嘘に聞こえてつらい」と感じるあなたは、きっとこれまで、人の期待や評価の中で一生懸命に頑張ってきた方なのだと思います。
人の言葉に敏感で、責任感が強くて、だからこそ“本当に信じていいのか”をずっと心の中で問い続けてきたのかもしれません。
このブログでは、以下のようなことをお伝えしてきました。
- 「褒められると辛い」と感じる心理の正体(インポスター症候群)
- 嘘に聞こえてしまう人に共通する特徴
- アダルトチルドレンや愛着の影響との関連性
- 放置することで生じる心のリスク
- 心のクセと向き合うための考え方と行動のヒント
読みながら「これ、私のことかも」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。自分の反応には意味がある——その視点を持つことが、変化の第一歩です。
専門家に相談してみませんか?
長年続いてきた「受け取ることの難しさ」や、「認められることへの不安」は、 ときに一人では整理が難しく感じるものです。
✅自分のことをうまく言葉にできない
✅気持ちがぐるぐるしてしまう
✅喜ぶべきなのに、どうしてもザワザワしてしまう
そんなときは、安心できる場で、やさしく一緒に見つめ直す時間が大きな支えになります。
当カウンセリングルームでは、「褒められるのが苦しい」「人からの言葉を信じられない」——そんな気持ちに寄り添うための 「お試しカウンセリング」をご用意しています。このセッションでは、
✅なぜ褒め言葉がうまく受け取れないのか?
✅その背景にある心のパターンや体験は何か?
✅どうすれば少しずつ“受け取ること”に慣れていけるのか?
を一緒に丁寧に整理していきます。
「話すだけでもいいかな」と思えたら、どうぞお気軽にご利用ください。
お試しカウンセリングの申し込み方法
お試しカウンセリングのお申込みは簡単です。 以下のお申し込みボタンから予約フォームにアクセスし、必要事項をご記入ください。
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、静かであたたかい空間をご用意してお待ちしています。
あなたが「信じたいけど、信じられない」と感じてきたその想いも、 ずっとひとりでがんばってきた心の証です。 それは、誰かに認められたくて必死だった過去のあなたが、いつも心の奥で「本当の私はどうなんだろう」と問い続けてきた証でもあります。
だからこそ、今この瞬間に少しだけでも褒められた言葉を「受け取ってみようかな」「信じてみたいかも」と思えたなら、 それはとても大きな変化のはじまりです。
あなたが、自分の気持ちを否定せずにいられる日が、少しずつ増えていきますように。
それが私の願いです。

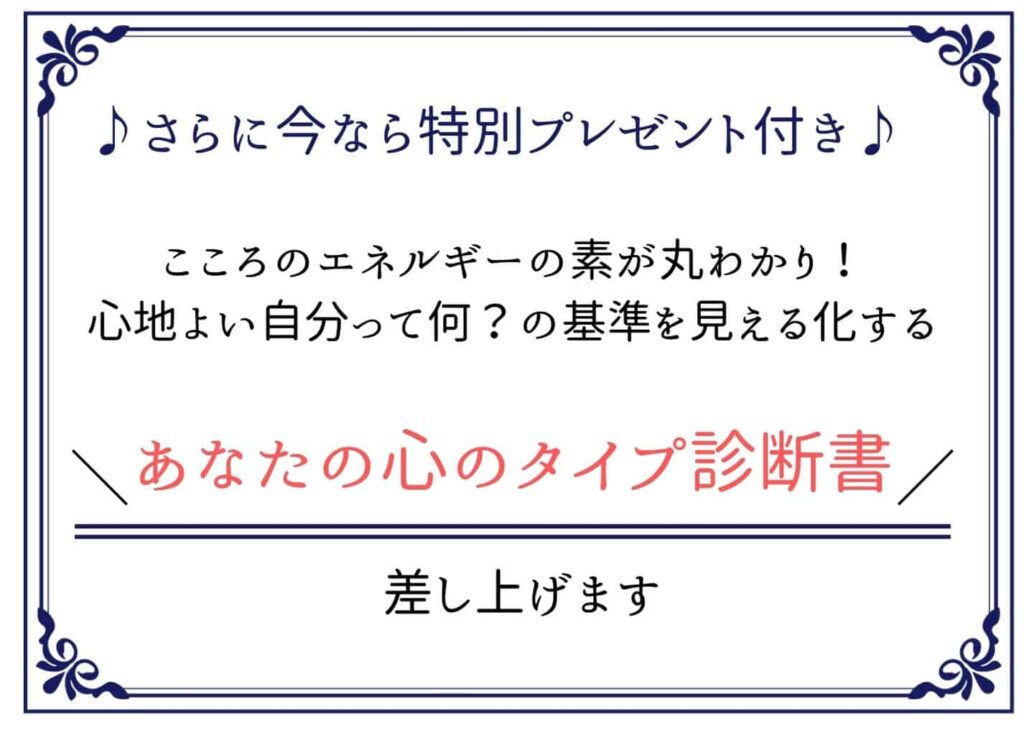
.png)




-293x300.jpg)