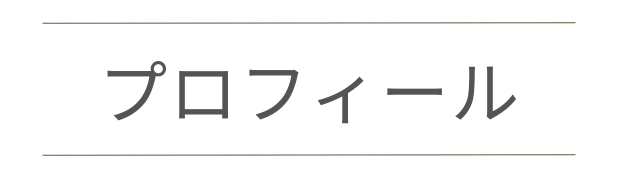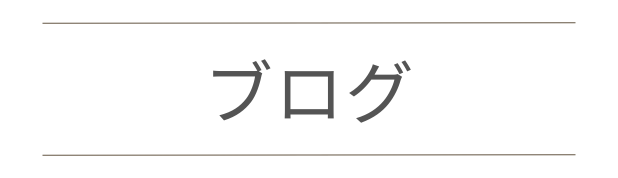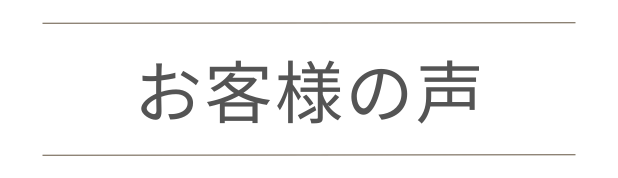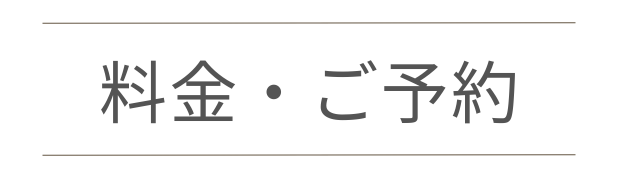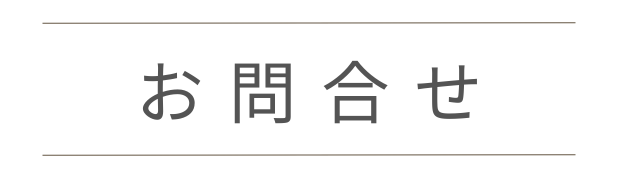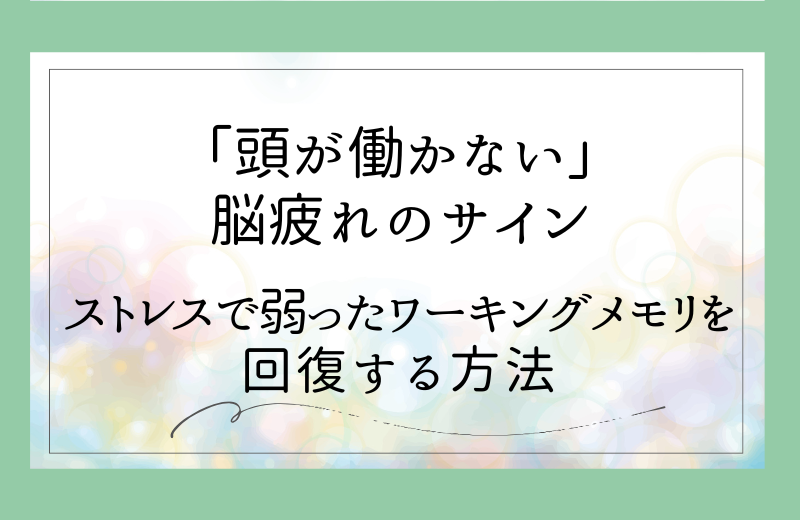
「最近、頭が働かない…」そんなふうに感じることはありませんか?
たとえば、仕事で何をすべきか考えがまとまらない、人の話を聞いても頭に入ってこない、やるべきことを思い出せない——。そんな思考のモヤモヤを感じている方が、今とても増えています。こうした状態が続くと、「自分がダメなんじゃないか」「もう年なのかも」といった否定的な思いにとらわれてしまいがちですが、実はこれは脳の疲れが引き起こす自然な反応のひとつかもしれません。特に、ストレスを慢性的に抱えていると、脳の中でも「ワーキングメモリ(作業記憶)」と呼ばれる部分が働きにくくなり、集中力・判断力・記憶力がガクンと落ちてしまいます。
このブログでは、「頭が働かない」と感じるときに脳で何が起きているのか、そしてどんなふうに脳の疲れを整えていけるのかを、わかりやすく解説していきます。
目次
頭が働かない「脳疲れ」とは
「なんとなくボーッとする」「会話の内容が頭に入らない」「考えるだけで疲れてしまう」——そんな状態が続いていませんか?
それは、ストレスや情報過多によって脳の処理機能が限界に近づいているサインかもしれません。ここでは、頭が働かないと感じる状態の背景にある「脳疲れ」とは何かを、脳のしくみとともにひもといていきます。「脳疲れ」とは、脳のエネルギーや処理能力が限界に近づいている状態を指します。一般的には「集中できない」「思考がまとまらない」「同じミスを繰り返す」などの症状として現れます。
これは単なるやる気や気の持ちようの問題ではなく、脳の神経活動の過負荷状態。特に前頭前野(思考・判断・感情のコントロールに関わる領域)が疲弊すると、ワーキングメモリの処理能力が著しく低下し、情報の整理・保持・活用が難しくなります。
※ ワーキングメモリとは、目の前の情報を一時的に覚えながら同時に処理する「脳の作業机」のような機能です。詳しくは次の章で解説します。
- 人の話を聞いても頭に入ってこない
- 複数のことを同時にこなそうとすると混乱する
- 「考えなきゃ」と思うのに、何も浮かばない
- メールの文章がいつまでも書けない
こうした現象は、脳の作業机が散らかっている状態ともいえます。情報を一時的に保持しながら処理する「ワーキングメモリ」は、容量に限りがあり、過度な刺激やストレスで簡単に“オーバーヒート”を起こしてしまいます。
自律神経の観点でも、ストレスが過剰にかかると交感神経が優位になり、脳の血流が低下。思考や集中の維持が難しくなります。
「どうして私はこんなに頭が働かないの?」と自分を責めることは、さらに脳に負担をかけてしまいます。まずは「これは脳の疲労反応なんだ」と知ること。認識するだけでも回復への一歩になります。
あなたのお悩みお聞かせください
↓ ↓ ↓
ストレスでワーキングメモリが落ちる仕組み
「やらなきゃ」と思っているのに、なぜか頭が働かない。焦るほどにミスが増えてしまう。そんな経験はありませんか?実は、強いストレスや心の緊張状態が続くと、脳の“作業机”であるワーキングメモリがどんどん狭くなっていくのです。
ここでは、ストレスが脳に与える具体的な影響や、ワーキングメモリがどのように機能低下していくのかを、脳科学と心理の視点からわかりやすく解説します。
ワーキングメモリは、よく「脳の作業机」に例えられます。作業机が広ければ複数の書類を並べて整理しながら仕事ができますが、狭い机では資料が山積みになり、必要なものを見失ったり、片づけるだけで精一杯になってしまいます。
ストレスが高まると、この作業机にどんどん「処理すべきこと」が積まれていきます。
たとえば、
- 頭の中で不安や心配事がループしている
- 周囲の人の視線や期待を気にしている
- 先のことを考えすぎて今に集中できない
こうした状態は、ワーキングメモリのリソースを浪費している状態。情報の整理や判断に使える領域が圧迫され、本来のタスクに集中できなくなるのです。
脳科学の研究では、強いストレスを受けると「コルチゾール」というホルモンが分泌され、前頭前野の機能が低下することがわかっています。
前頭前野はワーキングメモリを司る脳領域のひとつ。つまり、ストレスが強くなると、
- 「考えがまとまらない」
- 「順序立てて話せない」
- 「さっきの話を忘れる」
といった症状が出やすくなります。これは気持ちの問題ではなく、脳の構造的な反応なのです。
ストレスによってワーキングメモリが低下すると、
- 判断ミスやケアレスミスが増える
- 感情の起伏が激しくなる
- 落ち着きがなくなり、焦りやすくなる
といった状態が続きます。これは「能力がない」のではなく、脳が限界を迎えているというサイン。
次は、こうした状態に陥りやすい心理的傾向について、さらに深掘りしていきます。
ストレスで頭が働かない人にみられる心理的特徴
焦っても頭が働かない——そんな状態に悩む人には、ある共通した心理的な傾向があります。それは、意外にも「真面目でがんばり屋」「気配りができる人」たち。つまり、一見すると「できる人」に見える人ほど、実は脳に大きな負荷をかけている可能性があるのです。
では、ストレスによってワーキングメモリが疲れやすい人の心理的特徴について、詳しく見ていきましょう。
ワーキングメモリがストレスによって機能低下すると、「頭が働かない」「考えがまとまらない」といった症状が現れます。そして、このような状態に陥りやすい心理的特徴として、一見“優等生”に見える人たちが挙げられます。
- 真面目で責任感が強い
- 小さなことにも気を配る
- ミスを極端に恐れる
- 空気を読みすぎて自分の考えを後回しにする
こうしたタイプの人は、常に「うまくやらなければ」「ちゃんとしなければ」と自分に高いハードルを課しているため、脳の“作業机”が常にいっぱいになりがちです。
気配りができて、人の期待に応えようとする姿勢は一見すばらしく見えますが、その裏では、
- いくつものタスクを同時にこなそうとする
- 常に先回りしてリスクを想定してしまう
- 小さなミスや表情の変化にも敏感に反応してしまう
といった状態が続きます。これにより、ワーキングメモリの領域が慢性的に圧迫されたままになり、「なんでこんなに疲れるんだろう…」と感じるようになります。
「人に迷惑をかけてはいけない」「完璧にこなすべき」「いつも頑張っている自分でなければならない」といった思い込みは、脳のストレス耐性を低下させます。なぜなら、常に交感神経が優位になり、脳が緊張状態に置かれるからです。
HSP(Highly Sensitive Person)の傾向を持つ人や、発達特性(ADHD・ASDなど)を持つ人においても、
- 感覚過敏
- 刺激への過剰反応
- 切り替えの難しさ
あなたのお悩みお聞かせください
↓ ↓ ↓
脳疲れを放置する危険性
「ちょっと疲れているだけ」と思ってやり過ごしていたら、気づいたときには何も手につかなくなっていた——。そんな状態に心当たりはありませんか?
脳疲れは、無理をしてがんばってしまう人ほど自覚しにくく、知らず知らずのうちに深刻化していきます。特にワーキングメモリが慢性的に機能不全を起こしていると、感情・意欲・行動のコントロールにも影響が及び、「もう無理…」と限界を迎えてしまうこともあるのです。
ここでは、脳疲れを放置することでどんなリスクがあるのか、そしてその先に起こり得る心の不調について、具体的に見ていきます。
ワーキングメモリの疲弊が進むと、「考えられない」「決められない」「動けない」という状態が日常化していきます。これは単なる疲労ではなく、脳の処理能力が限界を超えて機能不全を起こしているサインです。
こうした状態を放置すると、やがて感情や意欲の面にも影響が広がり、
- ちょっとしたことで涙が出る
- すぐに落ち込む・自己否定が止まらない
- 「なぜかわからないけど、全部やめたくなる」
といった形で現れます。
ワーキングメモリの低下状態が長期間続くと、脳があらゆる情報を処理しきれなくなり、適応障害などのストレス関連障害を引き起こすリスクも高まります。
たとえば、
- 仕事に行こうとすると強い不安や動悸がする
- 人と会うことが億劫になり、回避行動が増える
- 今までできていたことができなくなり、自信を失う
といった状況に陥ることもあります。これは、脳の限界を超えてしまった結果です。ワーキングメモリが慢性的に圧迫されると、感情のコントロールや行動の切り替えにも支障が出てしまい、適応力そのものが低下します。
- ミスが増えた
- 判断ができない
- 人とのやりとりが負担に感じる
こうした変化が見られたときこそ、「脳が疲れているサインかもしれない」と立ち止まることが大切です。放置してしまうと、「できない自分」に対する自己否定感が深まり、さらに脳に負担をかけるという悪循環に陥ってしまいます。気力の問題と片付けず、脳の状態を整える視点を持つことが、回復への第一歩になります。
脳の疲れを回復させる3つのアプローチ
では、「脳が疲れている」と感じたとき、どうすれば回復できるのでしょうか?
脳疲れは、睡眠不足やストレスだけでなく、考えすぎ、情報の詰め込みすぎによっても引き起こされます。大切なのは、頭を休ませるだけでなく、ワーキングメモリにやさしい行動習慣を取り入れることです。ここでは、脳の仕組みに沿って、ワーキングメモリを整えるための3つの具体的な方法をご紹介します。
脳の疲れを回復させるには、特別なトレーニングや努力よりも、日常の中で「脳を休める習慣」を取り入れることが効果的です。ここでは、脳科学の知見にもとづいた「ワーキングメモリを整える3つのアプローチ」を紹介します。
① 情報入力を減らす習慣私たちは日々、大量の情報を処理しながら生活しています。 とくにワーキングメモリが疲れているときには、次のような意識的な情報制限が回復の助けになります。
- スマホの通知をオフにする
- SNSやニュースのチェック時間を限定する
- 複数タブやアプリを開きすぎない
ワーキングメモリは「一時的な情報の保管庫」であり、過剰な入力は作業効率を下げ、判断力の低下につながります。
② 思考を外に出す習慣脳の中に情報をとどめておくと、処理が滞りやすくなります。 これを防ぐには、「考えること」を紙に書き出したり、誰かに話したりすることが効果的です。
- やることリストを作る
- モヤモヤする思考をメモする
- 頭の中の整理を声に出してみる
脳の疲れは、自律神経のバランスにも大きく影響を受けます。 とくにストレスが強いと交感神経が優位になり、脳の回復が阻害されます。そこでおすすめなのが、副交感神経を優位にする生活習慣です。
- 深い呼吸を意識する(4秒吸って8秒吐くなど)
- 寝る前にスマホを見ない
- やさしい音楽を聴く・自然音に触れる
- お風呂にゆっくり浸かる
これらはすぐに取り入れられるうえに、脳の回復モードを引き出してくれる行動です。
脳の疲れは、「根性」で回復するものではありません。 まずは脳の仕組みを理解したうえで、余白を取り戻す習慣を育てていくことが大切です。
あなたのお悩みお聞かせください
↓ ↓ ↓
会議中に頭の中が真っ白に|そのようなご相談に私ならこう向き合います
ネットでこんなお悩みを目にしました。
「会議中に急に頭が真っ白になって、何も浮かばなくなってしまいました。発言しようと思っても言葉が出ず、ただ固まってしまって…。自分でも何が起きたのかわからず、その後も仕事に集中できなくなってしまいました」
.jpg)
カウンセラーの田口れいです。
もしこの方が私のカウンセリングに来られたら、まずはこの出来事について丁寧にお話を聴きます。「何があったか」だけでなく、「そのとき何を感じたか」「自分をどう捉えたか」に焦点をあてていきます。
「きっと変に思われた」「迷惑をかけてしまった」という思いがある場合、それはとても自然な反応ですが、その裏側には“脳の限界”があったのかもしれません。まずは冷静に状況を見直せるよう、さまざまな質問をしながら、心と頭の整理をしていきます。
次に、どんな場面で同じような状態になりやすいか、どんな思考や癖が脳に負荷をかけているか、一緒に考えていきます。安心できる対話の中で、「ただの恥ずかしい失敗」だった経験が、「脳のSOSだった」と気づけるようになると、自分を責める気持ちが少しずつゆるんでいきます。
そして、この方が再び自信を取り戻し、自分のペースで発言したり、安心して働けるようになること。そのためにできることを一緒に探していきます。私がカウンセリングで大切にしているのは、「自分を責めずに安心して話せる場をつくること」です。頭ではわかっていても心が追いつかないとき、一人では整理できないとき、そっと一緒に歩く存在でありたいと思っています。
ご本人のペースを尊重しながら、少しずつ“考える力”や“感じる力”を取り戻していけるよう、対話のなかで伴走していきます。
セッションを受けられた方の体験談
このように、専門家のサポートを受けることで、自分の人生を取り戻すための適切な対策を取ることが可能になります。生きづらさを感じ、自分だけで対処しきれないと感じた場合は、ぜひ一度、カウンセリングを検討してみてください。
考える気力がなくなったと悩む方からのよくある質問
「頭が働かない」「考えようとしても動けない」——そんな状態を経験すると、不安や疑問が次々と湧いてくるものです。ここでは、脳疲れやワーキングメモリの不調に悩む方からよくいただく質問にお答えしていきます。
「物忘れ」と聞くと、高齢者や認知症のイメージが浮かぶかもしれませんが、それは「記憶そのもの」の保存や呼び出しに問題がある状態です。一方、「脳疲れ」はちょっと違います。記憶力そのものはあるのに、「今何しようとしてたっけ?」とすぐに抜けてしまったり、人の話を聞いていてもふっと意識が飛んでしまったり…。これは、脳の「作業机」にあたるワーキングメモリが、いっぱいになってしまっている状態。情報をいったん置いておくスペースが足りなくなって、処理しきれなくなってしまっているんです。
「一時的なオーバーフロー」とも言えるこの状態は、しっかり休んだり、少しだけ環境を整えるだけでも回復が見込めます。
それは、脳がいっぱいいっぱいになって「考えることをやめてしまっている」状態かもしれません。特にワーキングメモリが疲れていると、頭の中がこんがらがってしまって、「何から手をつけたらいいのか分からない…」というふうになりやすいんです。たとえば、パソコンを前にして「やらなきゃ」と思っているのに、なぜか手が動かない。メールを読んでも内容が頭に入ってこない。そんなときは、自分を責めるよりも、「今は脳が疲れてて、ちょっと休憩が必要なんだな」と受け止めてあげてください。こんなふうに自分にやさしくできると、脳もホッとして、少しずつ働けるようになっていきますよ。
いくつものことを同時にこなそうとして、全部が中途半端になってしまう…そういう時、ありますよね。
実は、私たちの脳の中には「一時的な作業スペース」のような場所があって、そこが「ワーキングメモリ」と呼ばれています。ここがしっかり働いていると、あれもこれも、ある程度スムーズに切り替えながら処理できるのですが、ストレスや疲れが溜まると、このスペースがどんどん狭くなってしまうんです。そうすると、あれもこれも…と手を出しすぎて、どれも中途半端になってしまったり、「あれ?今なにしてたっけ?」と混乱しやすくなってしまいます。
そんなときは、まず「ひとつだけに集中する」ことを意識してみてください。たとえば、家事なら「洗濯物をたたむだけ」「お皿を片づけるだけ」など、小さく分けて取り組むことで、脳の負担をぐっと軽くすることができます。
「うまくできない自分」を責めたくなるかもしれませんが、「がんばりすぎているサイン」。そんなふうに自分をいたわる目線で向き合ってあげられると、脳も少しずつ元気を取り戻していきますよ。
はい、そうなんです。頭が働かないときは、「がんばりが足りない」のではなく、むしろ「もう十分がんばってきた証拠」。脳が「ちょっと休ませて〜」とサインを出している状態なんですね。無理をして動こうとすると、ますますワーキングメモリが疲れてしまい、判断力や集中力がどんどん落ちていってしまいます。だからこそ、「今は立ち止まっていい」と自分に許可を出してあげることが、実は一番の回復への近道なんです。
意識的に「思考の余白」をつくることもとても大切です。ぼーっとお茶を飲んだり、何もしない時間を5分だけでも取ったり…。そんな小さな「ゆるめる時間」が、疲れた脳にとっては最高のごほうびになります。
「休むこと」=「悪いこと」ではありません。脳にとっては、それがちゃんと働けるようになるための大切なリセットなんです。
それはとても自然な感覚です。脳疲れは、体と違って目に見えないぶん、「大したことない」と思って無理をしてしまったり、つい一人で抱え込んでしまいやすいものです。でも、考えがまとまらなかったり、いつも通りに動けなかったりするときは、脳がちょっと限界に近づいているサインかもしれません。
そんなときに、誰かに話すだけでも、自分の気持ちが整理されたり、「そうだったんだ」と気づけたりすることがよくあります。話すことは、心と脳を一緒に整える「やさしいセルフケア」なんです。
そして、必要だと感じたときは、専門家に頼ることも自分を守る大切な手段です。「ひとりでがんばらなくてもいい」——そう思えることが、回復への大きな一歩になることもあります。
まとめ|脳をクールダウンし、健やかに過ごすために
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
いかがでしたか?
「頭が働かない」「思考がまとまらない」と感じるとき、それは脳が発している疲れたよというサインかもしれません。ワーキングメモリがオーバーヒートを起こすと、考えが整理できなくなったり、判断力や集中力が落ちたりして、ますます自分を責めてしまいがちです。
このブログでは、「頭が働かない」と感じるときに起きている「脳の疲れ」の正体と、その背景にあるワーキングメモリの働き、そしてストレスとの関係について丁寧にお伝えしてきました。さらに、こうした状態に陥りやすい人の心理的傾向や、放置した場合のリスク、そして脳を整えるための具体的なアプローチについても紹介しました。
「これ、自分に当てはまるかも」「ちょっとやってみようかな」と思えることがひとつでもあったなら、それはあなたにとって大きな一歩です。
ここまで日々の中でたくさんのことに気を配り、がんばってきたあなた。その努力や誠実さは、必ずどこかで誰かの力になっているはずです。でも、がんばり続けているときこそ、知らず知らずのうちに心や脳が疲れていることもあります。だからこそ、「ちょっと休もうかな」「少し整えてみようかな」と思えることがとても大切です。
このブログが、そんなふうに自分をやさしく見つめ直すきっかけになれていたら、心からうれしく思います。
専門家に相談してみませんか?
もし今、「心がしんどいな」「モヤモヤしていて整理できない」と感じているなら、カウンセリングという選択肢もあります。
当カウンセリングルームでは、思考の整理と心の休息を目的とした対話セッションを行っています。
- 話すことで頭の中が整理される
- 自分の考え方のクセに気づける
- 一人で抱えていた不安が軽くなる
初めての方のために「お試しカウンセリング」もご用意しています。どんな雰囲気か試してみたい、話すだけでもいい、そんな気持ちで気軽にいらしてくださいね。

お試しカウンセリングの申し込み方法
お試しカウンセリングは、お申込みは簡単です。
下にある「ご予約はこちらから」ボタンを押して予約フォームにアクセスし、必要事項をご記入ください。
初めての方でもリラックスしてご相談いただけるよう、安心できる空間をご用意してお待ちしています。
最後に、あなたが「自分のための時間」を心から大切にできるようになることを、心から願っています。これまで、たくさんのことに気を配り、人知れず努力してきたあなた。今こそ、自分にやさしさを向けるタイミングかもしれません。
私たちはいつも、誰かのために頑張りすぎて、自分のケアを後回しにしがちです。でも、あなたの心と脳が整ってこそ、本当に大切にしたい人たちを支える力も湧いてきます。「ひとりで抱えすぎていたかも」「ちょっとだけ頼ってみようかな」そんな想いが芽生えたなら、その気持ちを大切にしてみてください。
未来のあなたが、もっと軽やかに、もっと自然体で過ごせるように。
そのお手伝いを、ぜひ私にさせてくださいね。

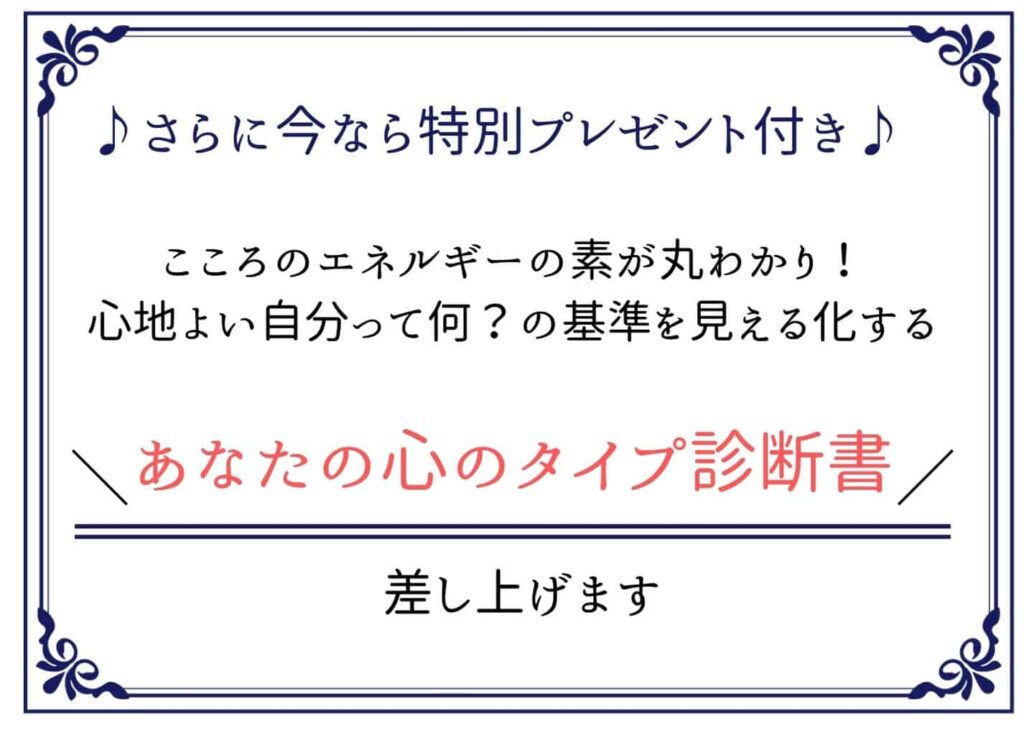
.png)




-293x300.jpg)